役所で参加者募集していたので、意見をまとめて書いてみた。応募のための文章の提出は800字ということだったけど、長すぎるので提出は取りやめることにした。自分の思いをまとめてみたけど、よかったら読んでみてください。
「私の考える高齢者の活躍と絆づくり」
1980年ごろ、大正生まれの叔母は戦後渡ったオーストラリアで苦労し年取ったので、日本の食事ができる日本の施設に住もうかと見学にやってきた。そのころの暗いイメージの日本の施設に来ることを私は反対した。
2000年から介護保険が誕生し、次々に新しい施設ができ、私の母や主人の母はいろんなサービスを受け天寿を全うした。
さて団塊の世代に近い私たちは、高齢者が人口の3分の1となると、生きるのも死ぬのも大変となる。
100歳までが当たり前に生きるというが、病院と施設にお世話になり、そうやって生きることが本当に世の中のためなんだろうかと疑問を抱く。「もう死んでしまいたいけど、今日はまだイヤ」とみんなは思う。倍賞千恵子の映画で「75歳」だったっけ?国の法案が決まって薬を打ってもらって死ぬ選択肢もいいなぁと思っていたけど、75歳近くになるとやっぱりまだ「今日はイヤ!」となる。
政策で体操を推進し、栄養のバランスを考え、サプリや薬を飲み、、、健康寿命を延ばしたとしても、やはり病院と施設のお世話にならなければならない。核家族ならお願いするしかない状態となる。一人暮らしも900万人とか、もうパンク状態ですね。
施設にお世話になると、死ぬまでやはり10年前後かかるのかもしれない。健康寿命を延ばす意味はどこにあるのだろうと思う。
介護を受けている人で、外国人の介護士が嫌だという人もいたが、大学を出たような外国人が来てくれているのだから、介護を受けるほうの度量も広げていかねばならない。
英語の通じない日本、給料の安い日本は、そのうち見限られることになるでしょう。
高齢者の関心はどこにあるのか。高齢者と言っても、生まれた場所、人生の歩み方、収入や財産…などで考え方はずいぶん違ってくる。
昔の老人は、わりあい「有難い、有難い」を言っていたように思う。ずいぶん苦労したからだと思う。今はどうだろう、若々しくいられること、きれいでいられること、健康でいられることに世の中もシフトしすぎではないだろうか。自分さえよかったらいい?
高齢者には年齢なりの美しさを見せていただきたいと思う。これは表面的な問題でなく、心や考えの問題ではないかと思う。
老人大学や老人センターなど開催していただいているが、もっと年代の違う人と自由に学べる場所を作っていくのはどうだろう。学校制度や時代の流れで、同年代に近い人しか交流がないのは、地域活動をする上で障害になると思う。
リージョンセンター(市民プラザ?)は東大阪市で核となる場所です。そこでしっかりと学び合える場所を確保していくことは大事なことと思います。単なるお稽古事としてとらえるのではなくて、時代に合った学びですね。いろんな人生を経験してきた人たちですから、きっと講師になってくださる方も多いと思います。それをどうやって発掘していくかというのは問題ですが、本来なら企画運営委員が作り出すべきかもしれません。
自治会も加入者が減り、班長のなりても少なくなって、子ども会も子どもが少なくなって存続も難しい。一人暮らしばかりが増えても交流が少ない。
地域でサロン活動を推進していても、運営費のねん出が難しく、ボランティアが持ち出しということもある。そういうところに、新しい人材が入って欲しいうのは難しい。
若い人たちにはある程度の対価があってしかるべきかと思う。役所にもお金はないのだけれど、ボランティアという言い方で、ただで人材を使おうとしている政策があり、それではいい人材は集まらないのではないかと危惧する。
思いがいっぱいで、文章が長くなりました。本当に高齢を生きるということに悩んでいます。もうすぐ後期高齢者を迎えますが、「高齢を生きることを考えよう」という呼びかけに賛成いたします。ありがとうございました。(終わり)
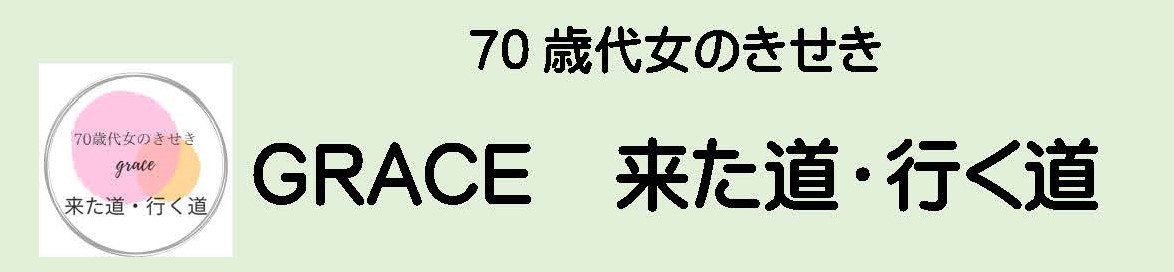


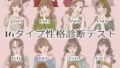
コメント